(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
はじめに
障がい福祉事業では、利用者様の生活リズムや家族の就労状況に応じて柔軟にサービス提供時間を調整することが求められます。2024(令和6)年度の報酬改定では、生活介護の基本報酬が利用時間に応じた体系に変わり、9時間以上の支援を「延長支援加算」として別途評価する仕組みが整備されました。今回は、延長支援加算の概要や算定要件、延長時間帯に必要な職員配置について説明します。
延長支援加算の概要
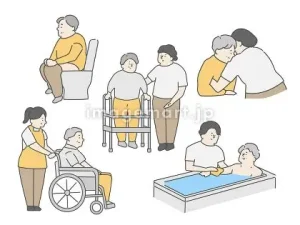
- 所要時間9時間以上10時間未満:100単位/日
- 所要時間10時間以上11時間未満:200単位/日
- 所要時間11時間以上12時間未満:300単位/日
- 所要時間12時間以上:400単位/日
ここでいう「所要時間」は生活介護計画に記載した標準時間ではなく、実際にサービスを提供した時間を意味します。送迎のみの時間は含まれず、利用者が施設内で支援を受けている実時間を積み上げて算定します。
延長支援加算の算定要件

①実際の支援時間を記録する
加算を算定するには、利用者ごとに実際の支援開始・終了時刻を記録し、9時間を超えた部分がどの区分に当たるかを確認する必要があります。時間区分に応じた加算額が異なるため、職員配置や利用者のスケジュール調整を行いながら無理なく運用することが大切です。
②延長時間帯の職員配置
延長支援加算で最も注意すべきは、延長時間帯に配置すべき職員の要件です。報酬改定通知では「延長時間帯に、指定障害福祉サービス基準により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る)を1名以上配置していること」と明記されています。
この規定は、通常の運営時間帯と同様に利用者の安全を確保するための最低ラインであり、利用者数や支援内容によっては複数名の配置が必要になる場合もあります。
また管理者やサービス管理責任者は、直接支援業務に従事していない場合にはこの「直接支援職員」としては認められません。したがって、延長する時間帯に利用者が1人であっても、最低1名の生活支援員等が残って支援にあたる体制を整える必要があります。
③事前の届出
運営時間の変更や延長加算の算定には、自治体への変更届出や加算届出が必要です。加算の算定開始前に必ず届出を行い、受理されてから適用するよう注意してください。届出書類や提出期限は自治体によって異なるため、早めに担当窓口へ確認することをお勧めします。
実務運用のポイント
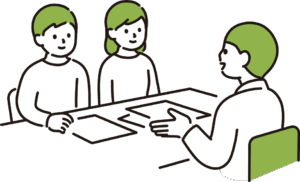
①利用者のニーズを把握する:
利用者やご家族がどのくらいの時間延長を希望しているかを把握し、個別支援計画に反映します。長時間の利用が常態化している場合は、他サービスの併用や短期入所の活用など別の支援策も検討します。
②職員体制の工夫:
延長時間帯に生活支援員を確保するためには、シフトの工夫が必要です。昼間の人員体制を過剰に削ると通常時間帯の質に影響するので、利用者数に応じて適切な人員配置計画を立てましょう。利用者が少人数であっても法令上最低1名は必須です。
③サービス管理責任者は別枠で確保:
サービス管理責任者は基本的に専門職として計画作成やモニタリング業務を行うため、延長支援加算の直接支援職員には含められません。延長時間帯にサービス管理責任者しかいない状態にならないよう、必ず生活支援員等を配置してください。
④自治体との連携:
延長支援加算の詳細な運用は自治体によって若干異なる場合があります。不明点は管轄の市区町村や都道府県担当者に確認することで、後日の返還や加算対象外となるリスクを減らせます。書類の提出漏れや遡及請求の可否など、行政手続きに精通した専門職に相談することも一手です。
おわりに
延長支援加算は、長時間支援が必要な利用者に柔軟に対応するための仕組みであり、単なる報酬上の加算ではありません。実際の支援時間を適切に記録し、延長時間帯には生活支援員等の直接支援職員を最低1名配置することが求められます。
今回の説明は経験をもとに制度の概要を整理したものであり、具体的な運用にあたっては最新の行政通知や各自治体の担当窓口に確認することをお勧めします。延長支援加算を正しく理解し、利用者にとって安全で安心な支援を提供する一助となれば幸いです。
