(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
はじめに
障がい福祉サービス・児童福祉事業所にとって、人員配置基準の遵守は事業運営の根幹と言えます。基準を満たせなければ報酬の減額に直結します。その代表的な仕組みが「サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)」です。
今回は、「サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)」とはどのように判定されるか、減算率・開始時期はどうか、などを整理し説明します。
-
サービス提供職員欠如減算とは
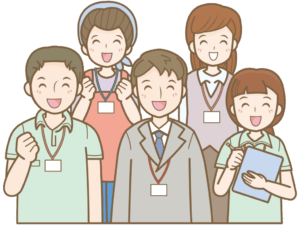
- 「サービス提供職員」(利用者に直接支援を行う職員)が基準より不足した場合、全利用者分の所定単位数に減算係数がかかる制度です。
- 減算率は段階制で、以下のように厳格に設定されています。
- 1~2か月目:所定単位数の 30%減算(係数0.7)
- 3か月目以降:所定単位数の 50%減算(係数0.5)
欠如が長期化すると収益が半減するため、経営に直結する大きなリスクです。
-
減算開始時期を分ける「1割ルール」
不足が発生したとき、その翌月から減算となるか、翌々月からかは「不足率」で決まります。
- 基準から1割を超える不足
→ 欠如が生じた月の翌月から減算開始。 - 基準から1割以内の不足
→ 欠如が生じた月の翌々月から減算開始。
ただし翌月末までに基準を回復すれば減算は不適用。
※不足率=(不足人数 ÷ 延べ必要員数)で算出します。
-
対象となる主なサービス
成人系(日中活動・居住系)
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
児童通所支援(対象となるもの)
- 児童発達支援(一般型)
- 放課後等デイサービス(一般型)
※児童通所支援(対象外となるもの)
- 児童発達支援センター
- 重症心身障がい児を主として通わせる事業所
これらは配置基準やサービス特性が異なるため、欠如減算は適用されません。
-
欠如の判定方法(児童福祉施設の実務例)
児発・放デイでは利用児数に応じて必要職員数が変動するため、月単位の延べ必要員数で判定します。
手順
- 各営業日の必要職員数を算出
- 合計して「延べ必要員数」を出す
- 実際配置した「延べ配置数」と比較
- (延べ必要員数-延べ配置数)÷ 延べ必要員数=不足率
判定例
- 月の延べ必要員数=42人
- 実際配置=41人(1日だけ1名不足)
- 不足率=1 ÷ 42 ≒ 2.4%(1割以内)
→ 翌月からではなく翌々月から対象。ただし翌月末までに解消すれば減算なし。
一方、5日分不足(不足5人)の場合:
- 不足率=5 ÷ 42 ≒ 11.9%(1割超)
→ 翌月から減算適用。
ポイント
「1日欠如=必ず減算」ではなく、不足率が10%を超えるか否かで扱いが変わるのが実務上の重要点です。
-
減算率と収益への影響
減算率
- 1~2か月目:30%減算
- 3か月目以降:50%減算
シミュレーション
所定単位数=1,600,000単位/月
- 1~2か月目:1,600,000 × 0.7 = 1,120,000単位(▲480,000単位)
- 3か月目以降:1,600,000 × 0.5 = 800,000単位(▲800,000単位)
→ 減算の有無や開始月の違いで、数十万円規模の収益差が生じます。
-
員数以外の欠如にも注意
- 常勤換算を満たしていない
- 専従配置の欠如
- 資格要件を誤認(児童指導員要件等)
これらも「員数欠如」と同様に減算対象。原則は翌々月からですが、翌月末までに解消すれば不適用となる場合があります。
-
減算を避けるための実務対応

- 代替要員の確保
→ 短期的な欠如に備え、非常勤や登録スタッフを確保。 - 月次シミュレーション
→ 延べ必要員数と配置実績を毎月計算し、不足率を把握。 - 1割ラインを常に意識
→ 1割以内なら翌月末までに解消で回避可能。 - 資格確認の徹底
→ 採用前に必ず証明書を確認、誤認による欠如を防ぐ。 - 自治体への早期相談
→ やむを得ない欠如が見込まれる場合は速やかに所轄庁へ相談。
まとめ
- サービス提供職員欠如減算は、人員基準を欠いた場合に所定単位数から30%~50%が減算される制度。
- 1割超なら翌月から、1割以内なら翌々月から。翌月末で解消すれば不適用になるケースもある。
- 児童発達支援センター・重症心身型児童発達支援・重症心身児対応の放課後等デイサービスは対象外。
- 1日だけの欠如でも不足率次第では減算に至る可能性があり、月単位での管理が不可欠。
- 減算は数十万単位の減収をもたらすため、代替要員確保と毎月のシミュレーションが事業継続の要です。

