(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
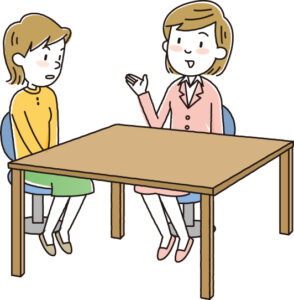
ピアサポートとは、障害当事者(または当事者経験のある人)が、自らの経験を活かして当事者に相談援助を行う支援です。就労支援B型では、生産活動の継続や地域生活の不安解消、就労意欲の向上に直結するため、制度として実施を後押しする目的でピアサポートが加算化されています。今回は「ピアサポート加算」について就労継続支援B型での算定について説明します。
-
目次
ピアサポート実施加算およびピアサポート体制加算の対象サービス
- ピアサポート実施加算(今回のテーマ)
- 就労継続支援B型、自立訓練(機能・生活)、共同生活援助
- ピアサポート体制加算(参考)
- 地域相談支援(地域定着支援)、地域相談支援(地域移行支援)、計画相談支援、障害児相談支援、自立生活援助
今回は 就労継続支援B型の「ピアサポート実施加算」 を中心に取り上げます。
-
所定単位数
- 100単位/月(1人の利用者につき)
当該月にピアサポートの相談援助を実施し、記録等の要件を満たした利用者ごとに算定します。
-
算定要件

-
人員・資格要件
以下いずれも満たすピアサポーターを事業所の従業者として2名配置。
- 地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」(基礎研修+専門研修)修了者
- 1の内1名は障害者または障害者であったと都道府県知事が認める者
- 事業所の従業者であること(雇用形態は問いません)
-
実施要件
- 当該障害者である従業者(=ピアサポーター)の経験に基づく相談援助を、利用者に対して実際に行うこと。
- 内容は、就労・生活上の不安解消、対人関係や体調配慮、工賃向上への意欲喚起など当事者経験に根差した助言・同行・ミーティング参加等を行うこと。
-
研修・普及要件(事業所内)
- 上記ピアサポーターが年1回以上、職員向けに「障害者に対する配慮等」の研修を実施していること。
-
記録・計画・同意について
- 個別支援計画等に位置づけ、実施記録(日時・実施者・内容・評価)を残し、本人同意の管理を行うこと。
- 様式は各自治体の通知・留意事項に準拠。
-
算定の具体例
- ピアサポーターA(当事者、研修修了・従業者)が、
- 利用者Xに:週1回の面談+作業場面のミニ振り返りを実施
- 利用者Yに:通院・服薬自己管理のコツを共有、作業配慮の助言
- それぞれ計画に位置づけ、記録と月次評価を残す。
→ X・Yそれぞれに100単位/月を算定(合計200単位)。
-
就労継続支援B型以外のサービスでの算定状況
-
自立訓練(機能・生活)
B型と同趣旨・同単位で「実施加算」を評価。
-
共同生活援助
入居中の実施に加え、退居後一定期間のピアサポートも評価対象(退居後ピアサポート実施加算)。
-
よくある誤解と実務の落とし穴

- 「ピアサポーターを置けば算定できるか?」
→ ×。「配置加算」ではなく「実施加算」です。当事者経験に根差す相談援助の実施と記録が前提です。 - 「非常勤で月1回の勤務でもよいのか?」
→ 雇用形態自体は不問です。ただし実施量が月算定に足る内容か、年1回の職員研修など他要件を満たしているかの確認が必要です。 - 「“ピアの視点”と一般相談の違いは?」
→ 支援の核が“当事者としての経験”にあるか。同じ助言でも、経験の共有・ロールモデル提示・失敗知の言語化など当事者性の発揮がポイントです。 - 「届出をせずに始めてよいのか?」
→ 不可。加算算定は事前の届出が原則です。
-
体制整備の手順
- 人材要件の確認
- 当事者/当事者経験者で、基礎+専門研修修了の候補者を確保。自治体主催研修の開催情報・申込枠を早めに確認する。
- 雇用・役割設計
- 従業者として雇用(非常勤可)。担当範囲・時間配分・記録様式を整える。
- 相談援助の運用設計
- 個別支援計画へ位置づけ(目的・頻度・場面)。同行やミーティング参加など、現場の生産活動と連動した導線を明記する。
- 職員向け研修(年1回以上)
- 配慮事項・合理的配慮の実践、ピア連携の留意点をテーマに、**開催記録(プログラム・出席・成果)**を管理する。
- 記録・評価
- 利用者ごとに実施記録(日時・内容・成果・次回予定)を作成し、月次で効果評価する。
- 届出
- 自治体所定の届出様式で申請し、算定開始月を確認する。
-
現場での活用方法一例
- 朝礼・終礼の“ミニピア”
作業前後の5~10分の振り返りをピアがファシリテート。体調自己把握・困りごとの早期共有につなげます。 - 作業工程の“つまずき地図”共有
当事者経験をもとに、疲れやすい工程・集中が切れやすい場面と対処法をリスト化し新人オリエンテーションで活用。 - 医療・家族・地域との橋渡し
通院同行や家族面談の際、当事者視点の言語化が安心感を高め、欠席・離脱の予防に寄与。 - 工賃向上アプローチとの組み合わせ
目標設定・成功体験の可視化をピアが支援し、動機づけと継続を促す。
-
まとめ(導入ポイント)
- 月100単位/人の評価ですが、目的は加算獲得ではなく支援の質向上です。
- 当事者経験×計画的相談援助が核となります。配置のみでは不可です。年1回以上の職員研修も必須です。
- 届出・記録・評価を丁寧におこなう。自治体の手引・様式に沿い、監査に耐える文書化を進める。
(参考資料)
ピアサポートの専門性の評価(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定)(厚生労働省)
令和7年度障害者ピアサポート研修事業 研修の参加にあたっての留意事項(管理者等版)(兵庫県)
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
