(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
令和6年度の障がい福祉サービス報酬改定により、「人工内耳装用児支援加算Ⅱ」が新設されました。これは、人工内耳を装用している児童に対して、言語聴覚士(ST)等の専門職の支援体制を整える事業所様を評価するものです。
今回は、加算の概要・要件・単位数・専門職の役割などを詳しく解説し、制度を適切に活用するためのポイントを整理します。
1.人工内耳装用児とは

人工内耳とは、重度から高度の感音性難聴の児童に対して手術で装着される医療機器であり、外部装置と体内装置を組み合わせて音の信号を内耳に直接伝えるものです。従来の補聴器では効果が得られにくい児童が対象です。
こうした児童が通う福祉施設では、専門的な言語支援や機器管理が必要不可欠です。
2.人工内耳装用児支援加算Ⅱとは
令和6年度報酬改定において新設された加算が「人工内耳装用児支援加算Ⅱ」です。これまで児童発達支援センター等の限られた施設でしか算定できなかった人工内耳児への加算が、より多くの一般通所施設でも算定可能となった点が大きな変更点です。
◆ 対象事業所
- 児童発達支援(センターを除く)
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
※加算Ⅰは従来から児童発達支援センター向けに設けられていたものであり、令和6年度の「新設加算」には該当しません。
3.加算の区分と単位数
| 区分 | 対象事業所 | 単位数/日 | 備考 |
| 加算Ⅰ | 児童発達支援センター | 445~603単位/日(定員による) | 既存加算(新設ではない) |
| 加算Ⅱ | 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス | 150単位/日 | 令和6年度新設加算 |
多くの民間通所事業所様が取得を検討するのは「加算Ⅱ」となります。
4.加算Ⅱの算定要件
加算Ⅱの算定には、以下のすべてを満たす必要があります。
① 人工内耳装用児の在籍
人工内耳を装用している児童が在籍し、当該児童の利用日ごとに加算が可能です。
② 言語聴覚士(ST)の関与
以下のいずれかの方法で支援体制を確保します。
- STを常勤または非常勤で配置
- 外部STと契約を結び、定期的な訪問や指導(例:月1回以上)を実施
③ 医療機関との連携
耳鼻咽喉科等の医療機関と連携し、児童の聴覚状況や機器の使用状況に関する助言・共有を受けていること。
④ 支援内容の記録
支援や相談援助の内容について、実施日時・概要を記録し、個別支援計画にも反映させる必要があります。
5.加算Ⅱの運用例と留意点
◆ 算定日と単位数
人工内耳を装用する児童が通所した日ごとに、150単位/日を算定可能です。
例)A児童が月15日利用:
→ 150単位 × 15日 = 2,250単位/月
※現時点で月単位での算定上限は設けられていません。
◆ 言語聴覚士(ST)と連携の場合の注意点

STを自施設で雇うことが困難な場合、外部との連携(嘱託・委託)で要件を満たすことができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- STによる支援や助言の記録があること
- 訪問・相談内容を支援計画に反映していること
- 医療的観点からの助言・共有が確保されていること
6.人工内耳児支援における現場の課題と期待
人工内耳は精密な医療機器であるため、故障や誤装着への対応、保護者支援を含む多角的な支援体制が求められます。言語聴覚士の関与は、児童の言語発達を促進するだけでなく、他職種との連携強化にもつながります。
この加算制度は、そうした多面的な支援の強化を促す重要な位置づけにあります。
7.導入検討にあたってのチェックポイント
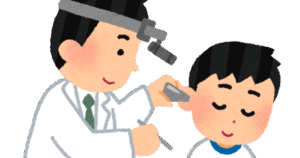
- 人工内耳装用児が在籍しているか?
- STが配置可能か、または連携体制を確保できるか?
- 医療機関との助言・情報共有の仕組みはあるか?
- 相談援助や支援内容の記録様式は整っているか?
こうした点をあらかじめ整理することで、スムーズな加算算定が可能になります。
8.参考資料
※ 自治体ごとに運用ルールが異なる場合があるため、事前に各所管課への確認が重要です。
おわりに
「人工内耳装用児支援加算Ⅱ」の新設は、人工内耳を装用する児童への支援の質を高める大きな一歩となります。
現場の負担軽減や児童の成長支援に向けて、加算制度の理解と適切な体制整備が今後より重要になっていくことでしょう。
