(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。

令和3年度報酬改定で創設され、令和6年度改定でも取り上げられている「地域協働加算」は、就労継続支援B型の利用者様が地域で活躍できる場を広げることを目的とした加算です。従来の「施設外就労加算」に代わる位置づけで、地域住民や地元企業、自治体などと協働しながら、利用者様が生産活動等に参加する取組を評価します。
一方で、「どのような活動なら算定できるのか」「レクリエーションやボランティアも含まれるのか」といった点は、現場で判断に迷いやすいところです。
今回は、就労継続支援B型における地域協働加算のポイントを整理し説明します。
目次
- 対象サービス名
- 算定加算単位
- 地域協働加算とは
- 算定の基本要件
- 望ましい取組例と、不適切とされる取組例
- 他加算との関係・実務上の注意点
- まとめ
1.対象サービス名
地域協働加算が算定できるのは、就労継続支援B型のみです。
さらに、「就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)又は(Ⅵ)を算定している事業所において…」とされており、該当の報酬体系を選択している事業所が前提となります。
2.算定加算単位
-
- 1日につき 30単位 を加算
就労継続支援B型は1日あたりの基本報酬に対する加算構造ですので、
地域協働の取組に参加した利用者1人ごとに、30単位が上乗せされるイメージです。
3.地域協働加算とは(趣旨と位置づけ)
3-1 創設の背景
令和3年度報酬改定で、就労継続支援B型における「施設外就労加算」が廃止され、
それに代えて創設されたのが地域協働加算です。
- 利用者の地域での活躍の場・活動の場を広げること
- 地域住民等と協働する取組を通じて、地域の活性化や障害への理解促進を図ること
を目的とされています。
3-2 地域協働加算の位置づけ
- 「就労継続支援を利用する障害者が、地域の中で様々な役割を果たすこと」
- 「地域住民との交流や、地域づくりに貢献する取組」
を評価する加算であり単なる施設外就労や校外作業の“置き換え”ではない点が特徴です。
4.算定の基本要件
4-1 対象となる取組の目的
地域協働加算の取組は、次の2つの観点を満たす必要があります。
- 利用者の地域での活躍の場を広げること
- 持続可能で活力ある地域づくりに資すること
つまり、売上アップだけを目的とした外部作業ではなく、地域社会との関わりや、住民との交流がきちんと意識されているかが重要になります。
4-2 地域住民・関係者との「協働」
加算名のとおり、「協働」であることが必須です。
- 地域住民
- 地元企業・商店街・農業者など生産者
- 自治体職員や商工団体
- NPO・自治会・町内会 など
と一緒になって取り組むことが求められます。
事業所単独で活動場所を借りて作業しているだけでは、「協働」とまでは言いにくいケースが多いです。
4-3 生産活動等への参加
Q&Aでは、「事業所内で雑貨・食料品の小売や飲食店を営業している場合はどうか」という質問に対し、
- 地域住民が来店し交流が生じているか
- 利用者が接客や販売などの役割を果たしているか
といった観点から、利用者の地域での活躍の場が広がっていると認められるものは対象となり得るとされています。
単なる内職や単純作業だけを地域で行うのではなく、
地域とつながりを持った生産活動・サービス提供であることがポイントです。
4-4 取組内容の公表
報酬の解釈や自治体通知では、地域協働の取組内容について、
- 事業所のホームページ
- ブログやSNS
- 自治体の情報サイト 等
を活用し、利用者や地域住民に向けて分かる形で公表することが求められています。
「いつ・どこで・誰と・どのような活動を行ったか」を写真・文章・工賃の状況などとあわせて公開しておくと、後の運営指導でも説明しやすくなります。
4-5 届出と記録
- 地域協働加算を算定するには、事前の届出が必要です(毎月15日までが一般的)。
- 実際の取組については、
- 参加した利用者
- 活動内容
- 実施日・時間
- 協働先
- 生産活動収入の状況 等
を記録として残しておく必要があります。
5.望ましい取組例と、不適切とされる取組例
5-1 望ましい取組例(イメージ)
- 地域の祭りやイベントに、店舗やブースを出して販売・サービス提供を行う
- 商店街や公共施設で、地域住民と一緒に清掃活動・美化活動を行う
- 地元カフェや物産店の一角を借り、利用者が接客・販売を担当する「共同店舗」を運営する
- 地域の農家と連携し、収穫体験と併せて、収穫物の加工・販売まで行う など
いずれも、「地域住民との交流」や「地域の課題解決への貢献」が意識されています。
5-2 不適切とされる取組例(イメージ)

- 事業所の敷地内だけで完結する活動で、地域住民等との交流がほとんどないもの
- レクリエーションや観光を主目的とし、地域の課題解決や活躍の場の拡大に結び付かないもの
- 生活訓練の一環としての散歩・買い物程度で、地域との協働とは言えないもの
地域協働加算は「地域連携」「活躍の場の拡大」がキーワードですので、作業内容だけでなく、「誰と」「どのように」取り組むかが問われると考えると分かりやすいと思います。
6.他加算との関係・実務上の注意点
6-1 重度者支援体制加算・目標工賃達成加算との関係
就労継続支援B型では、
- 重度者支援体制加算
- 目標工賃達成加算
など、工賃や支援体制に関する加算が複数あります。
具体的な取扱いは自治体通知等で確認しておく必要があります。
6-2 生産活動収入・工賃との関係
地域協働加算の取組は、多くの場合、生産活動収入を伴います。
- 地域協働の活動で得られた収入は、他の生産活動と同様、工賃支払いの原資として位置づけることが想定されています。
- 目標工賃達成加算や平均工賃月額に影響する場合もあるため、活動ごとに売上・経費・工賃を整理しておくことが大切です。
6-3 安全管理・労務管理
地域での活動が増えると、
- 移動中の事故リスク
- 炎天下や悪天候での作業負荷
- 販売・接客時のクレーム対応
など、これまで以上に細かなリスク管理が必要になります。
個別支援計画・就労支援計画の中にリスク評価と対策をきちんと位置付けることをおすすめします。
7.まとめ
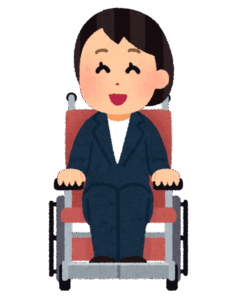
- 地域協働加算は、就労継続支援B型において、地域住民や地元企業・自治体と協働し、利用者の地域での活躍の場を広げる取組を評価する加算です。
- 対象は、就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵを算定する事業所で、1人1日につき30単位が加算されます。
- 「誰と協働しているか」「地域の課題や活性化にどう結び付くか」「取組内容をどのように公表するか」が重要な視点であり、単なる外部作業やレクリエーションでは、趣旨に合致しない可能性があります。
制度の意図を踏まえつつ、地域の商店街や自治会、企業、学校などと対話を重ねていくことで、
利用者様の活躍の場を広げるとともに、地域との関係づくりにもつながっていきます。
各自治体での運用や必要書類は細部が異なる場合がありますので、具体的な算定や届出の前には、お住まいの自治体の通知・担当窓口での確認をおすすめいたします。
事業所ごとの創意工夫が反映されやすい加算ですので、「うちの地域ならどんな協働ができるか?」を考えるきっかけとして、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(令和6年2月6日)(厚生労働省)P31
