(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
児童福祉施設を設置・運営するにあたり、事業者の皆さまが最初に直面する重要課題の一つが、「採光・換気基準」に関する要件です。これらは厚生労働省の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づき、児童の保健衛生および安全に直結する設備要件として明記されています。
今回は行政書士としての視点から、必要な知識と準備すべきポイント、そして建築士との連携のあり方をご紹介します。
1.採光・換気が必要とされる理由
「採光(自然光の取り入れ)」と「換気(空気の流れ)」は、児童の健康と快適性を支える基本条件です。特に厚労省基準では、児童福祉施設の構造設備は「採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な配慮」をした設計が義務付けられています
建築基準法第28条・施行令第19条でも、児童福祉施設等の居室には、明確な比率で採光・換気のための窓や開口部を設けることが求められています
2.具体的な基準内容
採光
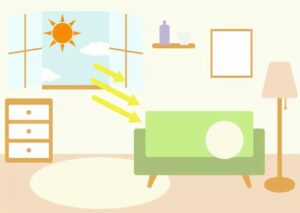
居室の床面積に対しての最低窓面積:
-
- 児童福祉施設では 1/7以上(一部施設は1/10まで)。
- 例:20㎡の部屋なら最低でも約2.86㎡、=南向きの大きめの窓が望ましいです。
換気
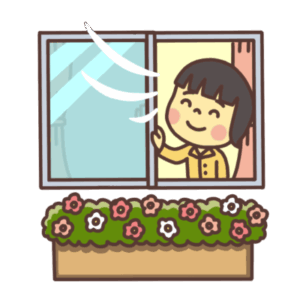
有効開口部面積:
-
- 居室の床面積に対して最低1/20(5%以上)、ただし大型の機械換気設備で代替も可能です
3.採光・換気を満たすための確認方法
大阪市をはじめ多くの自治体では、以下2つの方式で基準適合を確認するとされています :
建築士による証明
-
- 建築士(2級以上が一般的)が「採光換気証明書」を作成し、平面図と照合して基準適合を証明。
事業者(法人)による計測と申請
-
- 居室の面積と窓(開口部)を自ら計測し、「採光換気計算書」を作成・提出。条件外なら事業不可。必要に応じ、補正計算や機械換気を活用。
無窓居室(地下室など)では要件緩和もありますが、消防法や避難基準、シックハウス対策との整合性にも注意が必要です
4.建築士との連携ポイント

児童福祉施設の設置では、建築士との連携が不可欠です。以下ポイントを参考に円滑な協働を行いましょう。
-
事前相談:
候補物件が決まったら、まず建築士に採光・換気条件と平面図を提示し、事前に見積もりや検討を依頼します。
-
計算書作成:
建築士による「採光換気証明書」の作成には、採光補正係数や開口部の高さ・位置などの判断が必要です。専門的な計算や設計が求められるため、図面作成の段階からの関与が効果的です。
-
ミスの防止:
様々な理由で基準未達になると、指定申請が不受理になり、事業計画全体に影響します。万が一の場合に備え、建築士との図面チェック体制を整えましょう 。
5.準備ステップまとめ
以下のフローで進めると効率的です:
| ステップ | 内容 |
| ① 物件選定 | 南向き、外部に接する開口の多い物件を候補に |
| ② 建築士相談 | ①の図面をもとに採光・換気のチェック依頼 |
| ③ 測定・計算 | 平米数比率、補正係数を使って確認 |
| ④ 計算・証明書作成 | 建築士または自法人で計算し、書類整備 |
| ⑤ 指定申請 | 書類と平面図・建築士証明をセットで提出 |
なお、自然採光・換気が難しい狭小地や集合ビルの一室を使う場合は、機械換気設備による代替も視野に入れて設計段階で計画しておくことが現実的です。
6.行政書士としての支援内容
行政書士として提供できる支援:
- 児童福祉法・建基法等に基づく法的整理
- 書類作成(採光換気計算書、証明書、申請書類)
- 指定申請の代行および自治体との調整
- 建築士氏との仲介・要件整理サポート
おわりに
採光・換気の基準は、「窓の大きささえ確保すればいい」わけではなく、計算上の比率・設備・図面整備・補正係数・建築士との連携がセットです。見落とすと事業計画全体に影響が及ぶ可能性があります。
児童の健康と健全な施設運営のため、ぜひ本記事を設計・申請準備のベースとしてご活用ください。
ご不明点や書類作成の支援が必要な場合は、ご相談もお気軽にどうぞ(無料相談ではなく、個別見積りベースで承っております)。
