(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。

令和6年度の報酬改定では、障害児通所支援に新たに子育てサポート加算が創設されました。狙いは、従来の“連絡帳・面談中心”の情報共有にとどまらず、保護者が支援場面を観察・参加し、その場で並行して助言を受ける構造を制度として評価し、家庭での関わり方の再現性と連続性を高めることにあります。今回は「子育てサポート加算」について説明します。
目次
- 子育てサポート加算とは
- 対象サービスと単位数・算定回数
- 算定の基本要件
- 家族支援加算との関係
- 実務運用のポイント
- OK/NGの具体例
- よくある論点
- まとめ
-
子育てサポート加算とは
令和6年度報酬改定で新設。家族に「支援場面の観察や参加」の機会を提供したうえで、こどもの特性や関わり方に関する相談援助等を行った場合に評価する加算です。目的は、家庭と事業所の連携を「報告中心」から体験の共有とその場での助言へ転換し、家族の理解と養育力を高めることにあります。
-
対象サービスと単位数・算定回数
- 対象:障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
- 単位数:1回につき80単位。
- 回数上限:月4回を限度。
-
算定の基本要件
ポイントは次の2点です。
① 観察・参加の機会提供
家族が支援場面を直接観察・参加できるようにします。児の状態等から同席が難しい場合、マジックミラー越しやモニター視聴による観察も可能です。
② 相談援助は“その場で・並行して”実施
観察の機会に合わせ、支援を行う従業者とは異なる従業者が同時並行で相談援助を行うことが求められます。支援終了後にまとめて助言する形は想定されず、算定不可とされています。
-
家族支援加算との関係
同日算定は原則可能ですが、子育てサポート加算を算定する「同じ時間帯」に行った相談援助について、家族支援加算は算定不可です。時間帯を明確に分け、二重算定を回避してください。
-
実務運用のポイント

- 役割分担:観察・参加の場を設ける職員と、並行して相談援助を担う職員を明確に分け、勤務割で担保する。
- 計画・同意:個別支援計画に位置づけ、事前同意を得て実施。実施の頻度(上限月4回)と単位の根拠も内部規程に明記する。
- 記録:観察の方法(同席/モニター等)、助言内容、家族の理解・次回課題をその場で記録。後日まとめ書きでは「同時並行性」の実績が不明確になりやすいため注意してください。
- 物理的・機材面:マジックミラーやモニター観察を行う場合の視認性と音声の確保、個人情報保護の配慮(映像の録画可否や遮蔽の手順等)を運営規程に追記するのがおすすめです。
-
OK/NGの具体例
OK例
- 家族が別室のモニターで支援場面を観察。別の職員がその場で家族に個別助言(姿勢調整の声かけ方法、切り替えの合図の出し方等)を並行して行う。→ 算定可。
- 午前に子育てサポート(観察+並行助言)、時間帯を変えて午後に家族支援加算(個別相談)を実施。→ 両方算定可(時間帯の重複なし)。
NG例
- 家族が支援を見た後、支援終了後に一括で説明・相談。→ 子育てサポート加算は不可(同時並行要件に反する)。
- 同一時間帯に、子育てサポート加算の相談援助と家族支援加算の相談を同時にカウント。→ 不可(同時間帯の二重算定は不可)。
-
よくある論点
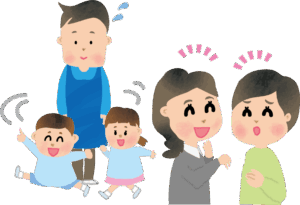
- 「時間帯を通じて」とは、ずっと同席が必要?
家族が観察や参加の機会を得て、その場で並行した相談援助を受けられる体制であることが要点です。常時同席が必須という趣旨ではなく、観察の機会+同時並行の相談援助を確保することが求められます。
- 兄弟が同日・同一の場で利用している場合の算定
それぞれ算定可能。ただし、保護者が一人でも、兄弟それぞれの特性に即した個別の相談援助が必要です。
-
まとめ
- 子育てサポート加算は、家庭との共体験とその場の助言を評価する新設加算。
- 1回80単位・月4回限度。運用は観察(参加)+同時並行の相談援助(別職員)がポイントです。
- 家族支援加算とは同日併算可ですが、同時間帯の二重算定は不可。時間帯管理と記録で担保するのがおすすめです。
実務では、役割分担・時間帯管理・記録の3点が品質と監査対応の要となります。
内部手順や様式の整備にあたっては、指定権者に確認の上、進めてください。
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)
