(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
家族支援加算とは、保護者や同居家族など「家族等」に対する計画的な相談援助を評価する加算です。通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用そのものを支えるだけでなく、家庭内の養育・生活上の困りごとを早期に掬い上げ、地域の支援資源とつなぐことを目的としています。今回は障がい児通所支援の「家族支援加算」について説明します。
-
目次
算定される単位数は?
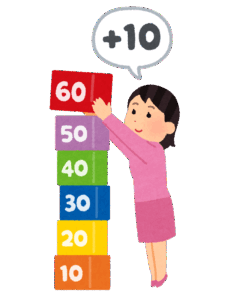
家族支援加算には個々の利用者様への相談援助の「家族支援加算Ⅰ」と数名のグループに相談援助を行う「家族支援加算Ⅱ」の2つの形態があります。
家族支援加算Ⅰ
(1) 居宅訪問での相談援助
-
- 所要時間1時間以上:300単位
- 所要時間1時間未満:200単位
(2) 事業所等での対面相談:100単位
(3) テレビ電話等の情報通信機器による相談:80単位
家族支援加算Ⅱ ※グループの目安は2~8名程度
(1) 事業所等での対面グループ相談:80単位
(2) テレビ電話等の情報通信機器によるグループ相談:60単位
※加算Ⅰ、Ⅱともに1日につき1回、かつ1月につき4回までが上限。
※30分未満の相談援助は算定不可(加算Ⅰの居宅訪問のみ、やむを得ず30分未満でも算定可の例外あり)。
ポイント
・同一日に(I)と(II)を実施した場合でも、それぞれの基準を満たせば個別に算定可能。
・通所支援を提供しなかった日でも、計画的に行った相談援助であれば算定可。ただし、その児童に当該月に通所支援自体の提供が無い場合は算定不可。
-
算定の要件とは?
- 同意と計画
- 通所給付決定保護者の同意をあらかじめ取得。
- 通所支援計画に、家族支援の目的・内容・頻度・方法を明確に位置づける。
- 実施の方法
- 職員(従業者)が計画的に実施すること。
- 加算Ⅰは居宅訪問、事業所対面、通信機器を用いた相談。加算Ⅱは事業所対面、通信機器を用いた相談。
- 加算Ⅱはペアレントトレーニング、ミニ講座、保護者会型の相談会など体系的・継続的なプログラムが望ましい。
- 記録について
- 実施日時、方法、対象者、相談内容、助言・調整、関係機関連携、評価を具体的に記録。
- 通信機器を用いた場合は、家族の通信環境・費用負担への配慮を事前確認した旨も残す。
- 頻度の上限
- 1日1回/月4回の上限管理。
- 対象の範囲
- 児童本人が同席していなくても算定可。内容が児童の育ち・生活の改善につながる相談援助であること。
3.実施場所・場面ごとの取扱い
- 保育所・学校等での実施も可。ただし、当該機関と緊密な連絡・役割分担を図り、計画的に行った場合に限る(突発的・単発の連絡対応は対象外)。
- 突発的な電話対応のみ、連絡調整だけでは原則算定不可(計画目的に基づく相談援助としての実体が必要)。
- 30分未満は原則不可。
- 例外:加算Ⅰの居宅訪問では、家族の事情等により短時間でも必要性が高い場合は可。
- 同一内容を複数の事業所で重複算定することはできません。同一日の他加算との関係は、告示・通知の重複算定禁止の原則に沿って整理を行う。
4.実務でつまずきやすいポイント

①「計画に書いていない」
最も多い減算・指摘要因です。家族支援の目標(例:朝の支度、服薬管理、きょうだい関係、登校しぶり、感覚過敏への配慮 など)と方法(個別/グループ、頻度、担当、関係機関連携)を計画に明記。支援記録と対応させておくこと。
② 連絡調整と相談援助の混同
幼保小学校・相談支援専門員・医療等との日程調整だけでは算定できません。家族の理解促進、具体的な行動変容につながる助言・トレーニング、資源紹介等の相談援助の実質が必要です。
③ 通信機器活用時の配慮不足
同意取得・環境確認・費用負担の配慮を記録。プラットフォームの指定はありませんが、個人情報保護と通信の安定を担保。ビデオOFFでの音声相談など、家庭の事情に応じた柔軟な運用も可能です。
④ 上限管理の欠落
1日1回/月4回を台帳で合算管理。個別・グループの別、方法別(居宅・対面・オンライン)も見える化して、請求漏れ・上限超過を防止。
5.具体例(記録に残す視点つき)
例1:居宅訪問(1時間20分)—加算Ⅰ-(1) 300単位
- 目標:朝の支度の段取りと視覚支援の導入。
- 内容:居宅で動線観察→絵カードの作成と配置→保護者へ手順化の助言・練習。
- 連携:学校担任へ連絡帳で共有、次回学校訪問を調整。
- 評価:登校までの所要時間が前週比-10分。次回までホームプログラム実施。
例2:事業所での対面(50分)—加算Ⅰ-(2) 100単位
- 目標:服薬忘れ対策。
- 内容:タイムスケジュール表の作成、タイマー活用、きょうだいへの声かけ方法。
- 連携:主治医からの服薬指示内容を確認。学校保健室への情報提供同意取得。
例3:オンライン(45分)—加算Ⅰ-(3) 80単位
- 目標:感覚過敏による外出困難への対処。
- 内容:ノイズ対策グッズの紹介、段階的エクスポージャーの計画作成。
- 配慮:家族側の通信環境・データ容量を事前確認(記録)。
例4:ペアトレ・保護者会(90分)—加算Ⅱ-(1)80単位
- ねらい:強化子育てスキルの共有と相互サポートの形成。
- プログラム:ABC記録の取り方、褒める頻度の自己チェック、ホーム課題。
- 参加:4家族。30分以上を満たし、月4回上限で運用。
6.関係機関連携の押さえどころ
- 相談支援専門員:計画相談の目標と整合。支援会議で家庭目標・担い手・頻度を共有。
- 保育所・学校:観察機会の確保と役割分担。授業観察や個別の指導計画と齟齬が出ないよう留意。
- 医療:服薬・感覚過敏・摂食など医学的助言の確認。同意を得て情報共有。
- 地域資源:子育て短期支援、家族会、レスパイト等へ具体的に橋渡し。
(※これらの調整だけでは算定対象になりません。相談援助と一体で行うこと。)
7.書類・記録フォーマット(最小限の例)

- 同意書:家族支援の目的・方法(居宅/対面/オンライン・グループ)・頻度・情報共有範囲。
- 家族支援計画:通所支援計画の一部として、目標→方法→評価指標をセットで。
- 実施記録:
- 日時/方法/所要時間
- 参加家族(グループは人数)
- 相談内容と助言・訓練内容
- 次回課題・連携先・評価
- 上限管理簿:日次・月次で加算Ⅰ、Ⅱの合算回数を管理。
8.よくある質問
- Q. 児童が同席しない面談でも算定できる?
→ 可。ただし児童の育ち・生活改善につながる相談援助であること。 - Q. 事業所サービス提供がない日に実施した面談は?
→ 可(計画的であれば)。ただしその月に当該児童への通所支援提供が全く無い月は不可。 - Q. 電話相談は?
→ 計画的なオンライン相談(テレビ電話等)として実施し、通信環境の配慮と同意を整えれば算定可。突発的な問い合わせ対応のみは不可。 - Q. グループの人数は?
→ 目安2~8名。30分以上が要件。
9.監査・指導で問われやすい論点
- 計画と記録の突合(同意・位置づけ・頻度・方法が一致しているか)。
- 上限の超過(1日1回/月4回)。個別とグループの合算管理ができているか。
- 内容の実質(単なる連絡調整ではないか。助言・訓練・資源紹介・フォロー評価があるか)。
- 通信機器利用時の配慮(手段の妥当性、費用負担への配慮、本人・家族の同意)。
- 他加算との重複(同一行為の二重評価になっていないか)。
10.まとめ
家族支援加算は、家庭での具体的な変化を後押しするための重要な評価です。
- 同意→計画→実施→記録→評価の流れを一体化。
- 個別/グループ/オンラインを適切に使い分け、上限管理を徹底。
- 保育所・学校・医療・相談支援と綿密に連携しながら、家族の自己効力感を高める支援を継続する。
これらを丁寧に整えることで、監査に耐えうる請求の適正化とご利用者様の満足度向上を両立できます。
また、運用については必ず事前に指定権者に確認の上、実施していただきますようお願いします。
【参考資料】
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)(厚生労働省)問28~32
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2 (令和6年4月12日)(厚生労働省)問2
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.4 (令和6年4月24日)(厚生労働省)問2、3
【参考文献】
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
