(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
障がい児通所支援事業所における自己評価は、支援の質の向上と透明性の確保を目的として、事業所全体で取り組むべき重要なプロセスです。令和6年度の報酬改定により、自己評価、保護者評価、(保育所等訪問支援では訪問先施設評価も含む)の実施と結果の公表が義務化されました。これらを怠ると、報酬の減算対象となる可能性があります。
今回は、事業所職員の皆様がスムーズに「自己評価シート」の作成を進められるよう、具体的な手順とポイントを解説します。
自己評価の全体像と目的
自己評価は、事業所の支援体制や運営状況を客観的に見直し、改善点を明確にするための手段です。職員全員が関与し、保護者や関係機関の意見も取り入れながら、支援の質を高めていくことが求められます。
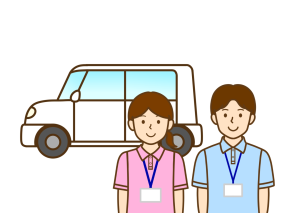
自己評価の具体的な流れ
ステップ1:評価シートの準備
まず、こども家庭庁が提供する評価シートを準備します。事業形態に応じて、以下のシートを使用します:
- 児童発達支援
- 従業者向け評価実施シート
- 保護者向け評価実施シート
- 自己評価総括表
- 保護者評価集計シート
- 事業者用自己評価シート
- 放課後等デイサービス
- 上記と同様のシートを使用
- 保育所等訪問支援
- 上記に加えて、訪問先施設向け評価実施シート、訪問施設先評価集計シート
これらのシートは、こども家庭庁の公式サイトからダウンロード可能です。
ステップ2:従業者による自己評価の実施
事業所の全従業者が、従業者向け評価実施シートを用いて自己評価を行います。各項目について「はい」「いいえ」で回答し、さらに「課題は何か」「工夫している点は何か」などの記述も求められます。このプロセスでは、職員全員の意見を反映させることが重要です。
ステップ3:保護者による評価の実施
保護者向け評価実施シートを配布し、保護者からの意見を収集します。回答は保護者評価集計シートにまとめ、特記事項欄の記述も含めて整理します。保護者評価は、客観的視点からの貴重なフィードバックとして、自己評価の際に活用します。
ステップ4:事業所全体による自己評価
従業者評価と保護者評価の結果を踏まえ、事業所全体で自己評価を実施します。この際、管理者だけでなく、全職員がミーティング等を通じて意見交換を行い、課題や改善点を共有します。自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」を分析します。
ステップ5:改善・充実に向けた検討
自己評価の結果をもとに、具体的な改善策や今後の取り組みを検討します。このプロセスも職員全員で行い、日々の支援に反映させることが求められます。
ステップ6:自己評価結果等の公表
自己評価結果は、インターネットや紙媒体を通じて公表します。公表する内容は、単なる集計結果ではなく、事業所の強みや弱み、改善に向けた取り組みなどを含めたものとします。また、保護者等へのフィードバックも重要です。

注意点とポイント
- 評価シートのカスタマイズ:事業所の実情に合わせて、評価シートを加除修正する場合は、国のガイドラインに沿った内容とすることが必要です。
- 評価の頻度:自己評価は、おおむね年に1回以上実施し、その結果を公表することが義務付けられています。
- 未公表による減算:自己評価結果を公表しない場合、報酬の減算対象となる可能性があります。例えば、児童発達支援や放課後等デイサービスでは、自己評価等未公表減算が適用され、基本報酬が85%で計算されることになります。

まとめ
障がい児通所支援における自己評価は、事業所の支援の質を高めるための重要な取り組みです。職員全員が積極的に関与し、保護者や関係機関の意見を取り入れながら、継続的な改善を図ることが求められます。適切な手順を踏み、評価結果を公表することで、信頼性の高い支援体制を築いていきましょう。
