(ご案内)就労選択支援の新設・指定をお考えの方へ。障がい(障害)福祉施設の指定申請サポートで、要件確認・様式作成・事前協議・消防/建築の確認まで伴走します(大阪・吹田/初回無料)。
令和7年10月1日から、新たに就労選択支援が始まります。これに先立ち、厚生労働省が令和7年9月5日付で「就労選択支援に関するQ&A VOL.1」を公表しました。初回版(VOL.1)の要点を整理し、実務で迷いやすい問2(兼務)と問6(福祉専門職員配置等加算)は深掘りします。モデル事業所の具体例も添えて説明します。
用語の確認(先にここだけ押さえると読みやすいです)
- 直接処遇職員:利用者に直接、支援・訓練・相談・看護等を行う職員です(例:サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員・就労支援員、看護職員、OT・PT、PSW、公認心理師 など)。※管理者・事務は原則含みません。兼務者は、実際に直接支援に従事した時間のみ「直接処遇」として扱います。
- 常勤:当該事業所が定める常勤の所定時間に達している勤務です。
- 常勤換算:延べ勤務時間を常勤所定時間で割った人数換算です。
例:1日4時間×週5日=0.5人(注:この例は「1日8時間勤務」を常勤所定時間とする場合です。各事業所の所定時間に合わせて読み替えてください。)
- 並行兼務不可:同一時間帯に2つの役割を同時に担うことはできません(時間帯で切り分ければ可)。
1.サービスのねらいと設備(問1)

問い: 指定就労選択支援事業所の設備は、同一敷地内の他事業(生活介護、就労移行、A型・B型等)と兼用できますか。
結論: 兼用できます(支援に支障がないことが条件です)。訓練・作業室の㎡基準は明示されていません。必要設備・備品は貸与でも差し支えありません。大切なのは、本人の希望・能力・適性に応じた多様なアセスメント手法・作業場面を常時確保しているかです。
イメージ: 図書館の会議室を時間帯で使い分けて自習にも活用するイメージです。使い分け+環境確保が満たせるならOK、という考え方です。
2.人員配置と「兼務」(問2)
問い: 就労選択支援員は、一体運営する生活介護・自立訓練・就労移行・就労継続A/Bの直接処遇職員と兼務できますか。
結論: 兼務できます。兼務した時間は就労選択側の常勤換算に算入できます。ただし同一時間帯の並行兼務は不可です(午前は生活介護/午後は就労選択、のように時間帯で切り分けます)。就労選択支援員の配置は「利用者15人につき1人(常勤換算)」が基本です。
[モデル事業所での具体像(生活介護)]
前提(勤務時間の想定): 本モデルでは1日8時間・週5日=40時間/週を常勤の所定時間として計算します。
体制: 生活介護…管理者兼サビ管1名/生活支援員=常勤換算2.0/常勤看護職員1名。現在、福祉専門職員配置等加算を算定中。
- パターンA:生活支援員1名が午前=生活介護(4h)/午後=就労選択(4h)で兼務します。
→ 就労選択側で0.5人(常勤換算)として配置に算入します。生活介護側も0.5人で再計算が必要です。同時間帯の並行は不可です。
→ 注意:人数は満たしても、「常勤」前提の加算には効かない場合があります(後述の問6参照)。
- パターンB:就労選択に“常勤”職員を新規配置し、既存職員は生活介護に専念します。
→ 15:1の配置を崩さず、双方の加算要件も整理しやすい運用です。
- パターンC:看護職が一部時間を就労選択へ充当します。
→ 兼務は可能ですが、配置基準(常勤換算)と加算(“常勤”・有資格者割合等)は評価軸が異なります。別々に試算するのが安全です。
実務のコツ(実務提案)
先に利用者の時間割(評価・作業場面)を設計し、その必要時間に合わせて兼務シフトを当てはめます。数字合わせから入るより破綻しにくくなります。
この設計順序は、問1の「適切なアセスメント環境の確保」と、問2の「同時間帯は並行不可」「常勤/常勤換算の定義」に基づく運用上の提案で、Q&Aの直接引用ではありません。最終判断は指定権者の運用に従ってください。
3.センター職員の従事・兼務(問3)
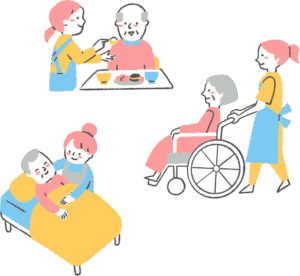
問い: 障害者就業・生活支援センターの生活支援担当は、就労選択支援員として従事(兼務)できますか。
結論: 従事できます。ただし、同一時間帯の並行兼務は不可です。地域資源との連携導線を活かしつつ、時間帯で役割を切り替える設計にします。
4.多機能型の「実施主体要件」の実績は合算可(問4)
問い: 多機能型(移行・A・B等)を実施主体として指定申請する場合、「過去3年で3人以上の雇用実績」は同一多機能内の複数事業の実績を合算できますか。
結論: 合算できます。(例:移行で1人+B型で2人=3人で要件充足)
5.同一法人の別事業所の実績は持ち寄り不可(問5)
問い: 同一法人内の他事業所での就職実績を流用し、自事業所の実施主体要件を満たせますか。
結論: できません。実績は事業所単位で判定します。
6.福祉専門職員配置等加算と兼務(問6)

問い: 生活介護などに常勤で配置される直接処遇職員が就労選択支援員を兼務する場合、就労選択側でも福祉専門職員配置等加算を算定できますか。
結論: この加算は**「当該事業所に“常勤”で配置される直接処遇職員」を基準に評価します。就労選択側での勤務が“常勤”時間に達していれば対象になり得ますが、常勤未満なら算定対象外です(資格割合なども当該事業所単位で判定します)。
[モデル事業所に当てはめる]
- ケース1:生活支援員Aが午後のみ就労選択(4h)を兼務
→ 就労選択側の配置(常勤換算0.5)には効きますが、“常勤”ではないため本加算の算定には原則寄与しません。生活介護側の分母・分子も動くため、両サービスで再計算が必要です。
- ケース2:有資格者Bを就労選択“常勤”で新規配置
→ Bは就労選択側の有資格者割合・常勤割合に直接寄与します。生活介護側の体制を崩しにくく、双方の加算最適化が図れます。
ワンポイント:配置基準(常勤換算)と加算は別物です。人数を満たしても加算が取れない落とし穴に注意しましょう。
7.情報公表制度の扱い(問7)
問い: サービス開始に伴う情報公表制度の報告は、いつから必要ですか。
結論: 就労選択支援は情報公表の対象ですが、就労選択向けのシステム改修中のため、令和7年10月1日時点の入力は不要、機能整備までは「未報告減算」を適用しない取扱いです(開始時期は追って周知されます)。
すぐに使えるチェックリスト
- 設備運用:評価・面談・作業の各場面を常時確保(静音・広さ・備品・動線/兼用可・貸与可)。
- 兼務設計:同時間帯の並行なし+15:1(常勤換算)を満たす。
- 実施主体要件:多機能型の合算可/同一法人別事業所の流用不可。
- 加算試算:就労選択側で常勤の直接処遇職員(有資格者)を誰に置くかを先に決める。
- 情報公表:開始時は入力不要・減算なしの暫定運用を最新周知で確認する。
おわりに(大切なお願い)
本稿は、制度開始に向けて現場ですぐ役立つ視点でQ&A(VOL.1)の要点を整理しました。最終の判断や運用は自治体(指定権者)で差異が生じ得ます。
最終判断は指定権者で異なる場合がありますので、導入前に必ず管轄へ事前確認をお願いいたします。
